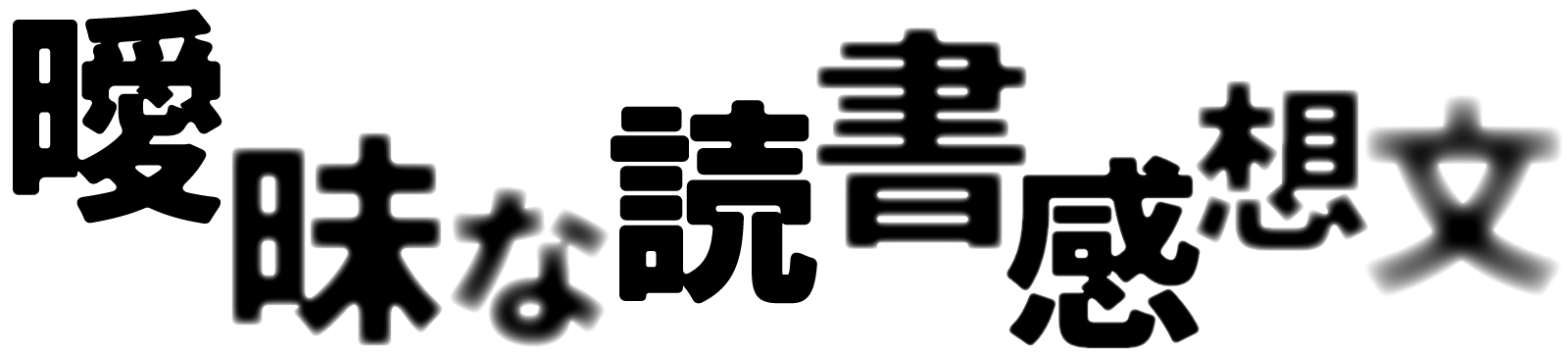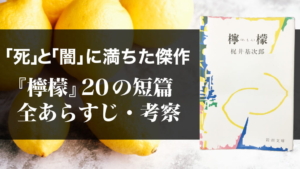32冊目『檸檬』梶井基次郎
明治の文豪シリーズ。31歳で亡くなった天才・梶井基次郎さんが、なんと24歳の時に世に放った傑作「檸檬」をはじめとする20編を収めた短編集。読めば読むほどにその才能が惜しまれる素晴らしい書。
時に鬱屈し、時に開放的になる感情がそのまま文章に変換されたような、生きている日本語の数々。生きていると言っても決して清々しいものではなく、割り切れない、得体のしれない重いものが胸のどこかに常につっかえている感覚で、全体的に少々暗めの文体です。
20篇すべてのレビューをネタバレありで書きました。
闇度(病み度)も自己採点で入れましたので、お口直し程度に…
ネタバレしても作品の良さは全く失われませんので、ぜひご自身で読む際の参考にしていただけたら幸いです。
『檸檬』梶井基次郎
文庫: 352ページ
出版社: 新潮社; 改版 (2003/10)
31歳という若さで夭折した著者の残した作品は、昭和文学史上の奇蹟として、声価いよいよ高い。その異常な美しさに魅惑され、買い求めた一顆のレモンを洋書店の書棚に残して立ち去る『檸檬』、人間の苦悩を見つめて凄絶な『冬の日』、生きものの不思議を象徴化する『愛撫』ほか『城のある町にて』『闇の絵巻』など、特異な感覚と内面凝視で青春の不安、焦燥を浄化する作品20編を収録。
梶井基次郎『檸檬』はこんな人におすすめ!
☑かつて国語で「檸檬」を読み、惹かれた事がある人
☑日本文学を感じたい人
☑闇のある小説が好きな人
☑読みやすい本が好きな人
☑とにかく、日本人なら読んどけ!
梶井基次郎『檸檬』収録の20の短篇それぞれのあらすじと感想・考察(ネタバレあり)
『檸檬』
言わずとしれた大傑作。「えたいの知れない不吉な塊」に心をとらわれていた「私」は、通りにある八百屋で一つの檸檬に魅せられ購入。ウキウキしていつもなら入るのを躊躇する京都の丸善に悠々と入り、画材を山の様に積み上げ、そのてっぺんに檸檬を置いたまま、爆弾に見立てて店を出る。「私」は、その檸檬が爆発する妄想を浮かべて嬉々としながら去っていく…と言うなかなかに病んだ話です。
このはたから見ると完全に不審者である「私」が、檸檬を愛でながら「つまりはこの重さなんだな」と納得してつぶやくシーンがもう一つのハイライト。自分を縛っている不吉な塊の重さがこの檸檬の重さなんだと気づいた時、ふっと「私」の心が軽くなる瞬間です。
人間は、何か別の対象に「自分の不安」を重ねることで、その不安の感情を一時的に同化させて紛らわして逃げることができます。ある意味飲酒や喫煙も同じではないでしょうか。「私」にとってその手段が檸檬を手に取り愛でることであり、爆弾に見立てて丸善を爆破する妄想にふけることだったのだと思います。
闇(病み)レベル:[jinstar4.0 color=”#ffc32c” size=”16px”]
『城のある町にて』
幼くして亡くした妹のことを落ちついて考えようと、姉の家に訪れた「彼=梶井基次郎」。
その心と呑気な日常の風景が混ざり合い、なんとも言えない郷愁を誘う短篇。
私がもし同じ立場なら。
どうしようもなく続く「翳りある日常」の存在は、決して憎くないけれど、言葉にならない感慨(或いは無力感)にゆっくり襲われるのだろうと思う。
セミの鳴き声「オーシ、チュクチュク」「スットコチーヨ」「ジー」が描く日常のワンシーンに代表されるような、音を取り入れた色彩豊かな表現が目白押しです。そこにいる動かない「彼」とのコントラスト。それだけでも楽しめるでしょう。
闇(病み)レベル:[jinstar3.0 color=”#ffc32c” size=”16px”]
『泥濘』
泥濘ーーぬかるみ。
創作活動に行き詰り、澱んだ気持ちのまま、家から届いた為替を換金するため本郷へむかう「自分(奎吉)」。
鉋屑、鏡、水差し、雪、石鹸、友人の顔…何を見ても不吉な予感、暗い想像が首をもたげる。気持ちは沈む。ビールを飲む。
酔いが回り、自分の名を呼んでみるも、嫌な思い出が蘇る。自分の影にさえ不安を感じる。
檸檬同様、主人公の暗い気持ちを表す表現が満載です。檸檬と違うのは、特に救いの様なものがない点。
でも、これも当たり前と言えば当たり前で、日常の中にそんなに都合よく救いは転がってはいない、と言うことでしょう。そんな無言のメッセージを感じます。
闇(病み)レベル:[jinstar3.5 color=”#ffc32c” size=”16px”]
『路上』
学校からの帰路、見つけた崖の近道で滑って転ぶ「自分」。
崖からは距離もあり、大事には至らなかった。
ただ、この姿を誰も見てくれていなかったと言う「恐怖」が湧き上がる。
死や破滅はこんな何気ない日常に潜み、突如ヌウと眼前に現れるのだ。
ーー破滅というものの一つの姿を見たような気がした。成る程こんなにして滑って来るのだと思った。
たった8ページの短篇ながら、言い知れない不安と焦燥、侘しさを感じさせる話です。
帰って鞄を開けて見たら、何処から入ったのか、入りそうにも思えない泥の固りが一つ入っていて、本を汚していた。
闇(病み)レベル:[jinstar2.5 color=”#ffc32c” size=”16px”]
『橡の花ーー或る私信ーー』
「私」の手記。
以前京都にいた時は毎年のように肋膜を悪くした、とあるので、「私=梶井基次郎本人」。
卑屈な想像、嫌悪感、不安感。
梶井基次郎のテーマが生活のシーンを切り取り語られるのは「城のある街にて」同様だが、本作では「他人」との関わりを通して明るい気持ちになって行く私の存在があります。
自分が小説家であることや、その活動と心の動きも語られるところで言うと、太宰治の作品群にも似た要素を感じます。
ただ、何回も女性と心中を計ったり薬に溺れたり解放運動に参加したり…誰がどう見ても激しい太宰治の人生に比べて、梶井基次郎の人生は誰がとチャンバラやり合うのではなく、内面を見つめる事が多かったからか、それとも単純に品が良いからか、文章に粗雑な感じがありません。
(念の為、太宰治の文章が乱暴だと言いたいのではないので誤解なきよう…)
こういった点も比較して読むと面白いのではないでしょうか。
闇(病み)レベル:[jinstar2.5 color=”#ffc32c” size=”16px”]
『過古』
梶井基次郎が大阪から東京へ上京し、その後三重へ移った際の心情を美しい表現で描いた詩的な短篇。
ここでは、夜の闇に身を委ねながら、マッチに火を灯すくだりが素晴らしい。
暗闇に点された火は、また彼の空虚な頭の中に点された火でもあった。
梶井基次郎は、心の闇と実際の闇とが同化して溶け合うような記述を得意としますが、この話でもその才能を発揮しています。
闇(病み)レベル:[jinstar3.5 color=”#ffc32c” size=”16px”]
『雪後』
大学で研究を続けながら結婚した「行一」の社会生活での不安と慎ましい生活ぶりを描く、読みやすい表情豊かな客観小説。
ロシアの小説の話、赤土から女の太腿がニョキニョキ出て来る夢の話、街の路上で牛が出産した話など、とても印象的で味わい深い一遍です。
闇(病み)レベル:[jinstar2.0 color=”#ffc32c” size=”16px”]
『ある心の風景』
悪い病気を女から得ていた「喬」の心象風景と、娼婦との時間、街を「病気」とともに歩きながら感じる気持ちを描いた短篇。
一つ一つの闇を感じさせますが、流麗な表現に感動すら覚えます。個人的にも好きな作品。
視ること、それはもうなにかなのだ。自分の魂の一部分或いは全部がそれに乗り移ることなのだ
時どき彼は、病める部分を取出して眺めた。それはなにか一匹の悲しんでいる生き物の表情で、彼に訴えるのだった。
闇(病み)レベル:[jinstar3.5 color=”#ffc32c” size=”16px”]
『Kの昇天ーー或いはKの溺死』
返信手紙の形で、Kの溺死の真実を告げる幻想的な短篇。
Kが海で溺死した。
Kと知り合って間もない「私」は、その事実を知り、「K君はとうとう月世界に行った」のだと言う。
K君は、影に魅せられた人間であった。特に月夜の自分の影をじーっと眺めていると、段々影こそが自分になっていく。
そしてそのまま、月の光線を遡り、自分の魂が月に昇天していく。
しかし、何遍やってもイカルスのように落っこちてしまうのだそうだ。
私は、魂の方が本体となって昇天することに成功できたからこそ、泳げるはずのK君の体は、ただの形骸になっていたので泳げなかった、そして無感覚のまま溺死したのだ、と言う。
梶井流・ダークファンタジーの真骨頂とも言えるこの短篇。あまりに美しく、静謐です。
闇(病み)レベル:[jinstar4.5 color=”#ffc32c” size=”16px”]
『冬の日』
病魔に侵された「堯」は、血の痰を吐くようになった。その冴え渡る赤色にも見慣れ、常々「死」を意識して暮らす。
死と隣り合わせに無気力に生きる。眼に入るもののすべてが堯を暗い気持ちにさせ、苛立たせる。
と、それだけの話ですが、いよいよ繰り出される言葉の数々の美しさはピークを迎えています。
夜と名附けられた日蔭
冷静というものは無感動じゃなくて、俺にとっては感動だ。苦痛だ。しかし俺の生きる道は、その冷静で自分の肉体や自分の生活が滅びてゆくのを見ていることだ
闇(病み)レベル:[jinstar4.5 color=”#ffc32c” size=”16px”]
『桜の樹の下には』
桜の樹の下は屍体が埋まっている!
衝撃的な一文で始まる、たった4ページの短篇。
桜が何故あんなに見事に咲くのか?
それは、桜の樹の下に屍体が埋まっているからだ。屍体から水晶の様な液体が染み出て、桜の本領を発揮させているのだ。
ハッキリ言って頭のおかしい話ですが、梶井基次郎の迷いの無い筆致に結局魅せられてしまうことでしょう。
死に真正面から向き合うことで、もはや死を取り込んでしまったのではないか。そんな事さえ頭をよぎらずにいられない、悪魔的傑作です。
闇(病み)レベル:[jinstar5.0 color=”#ffc32c” size=”16px”]
『器楽的幻覚』
クラシックのコンサート会場にて。
初めは曲を聴いていたものの、ライブ感〜群衆の動きというものにこの上ない違和感、孤独感、疎外感を感じる「私」が描かれるこれまた傑作。
華々しいはずのコンサート会場を舞台としたこの着眼点と、描かれる厭世観は超シニカル。
ここまでのひねくれ者にはなかなかお会いできません。存分に読み味わいましょう。
闇(病み)レベル:[jinstar5.0 color=”#ffc32c” size=”16px”]
『蒼穹』
ある晩春の午後、土堤の上で日を浴びながら、さらに動かない雲を見つめる「私」。
あの雲の中には何があるのか想像して、妄想して、一人愉しむが、やがて一つの真実に辿り着き絶望する。
世の中のあらゆるものだって、この雲と同じ様に豪奢に揺れながらも実は中身なんてなく、空っぽなのだ。
そんな痛烈な皮肉を感じさせる、割と優雅な短篇です。
闇(病み)レベル:[jinstar4.0 color=”#ffc32c” size=”16px”]
『筧の話』
物事にはすべて裏と表がある。
梶井風にいうならば、光と闇が。
その事に改めて本人が気づいた瞬間を切り取った、3ページ半の超短篇。
静かな、とても静かな物語です。
「私」が散歩に出る二つの道。展望がある反面集中力を削ぎがちな街道と、陰気だが心を静かにしてくれる山径。
山径を行く私が密かに楽しみにしていた、ある竹でできた筧。そこを流れる水の音を聴きながら、ふとその事実に至ります。
慎重で疑い深い梶井基次郎だからこそ得られた世界の見方。最後の一文が象徴的です。
「課せられているのは永遠の退屈だ。生の幻影は絶望と重なっている」
闇(病み)レベル:[jinstar1.5 color=”#ffc32c” size=”16px”]
『冬の蠅』
冬の蠅は、生命力がなく痩せ細っている。「私」は療養する家の軒先に現れるその弱った蠅に、それでも生きようとする生命の本能を見る。
ある日、数日間家に帰らず放蕩する私。久々に家に帰ると、冬の蠅は全て死に、いなくなっていた。
留守中、窓を開けて部屋を温め無かった私が、その蠅を殺したのだと気づく。
感傷に浸りながら、自分自身も、何かのきっかけで自分を殺し得るのだ、と戦慄する。
蠅を見る私が、いつしか蠅に同化する。そして、その私の哀れを、死にゆく蠅にすら見透かされている…そんな恐怖を日常の描写に合わせて感じさせる一篇です。
そこには感情の弛緩があり、神経の鈍麻があり、理性の欺瞞がある。これがその象徴する幸福の内容である。おそらく世間に於ける幸福がそれらを条件としているように。
闇(病み)レベル:[jinstar2.0 color=”#ffc32c” size=”16px”]
『ある崖上の感情』
カフェで出会った青年の生島、石田。
生島は、崖の上から様々な窓を覗き見する趣味がある。
その趣味は、人のベッドシーンを覗き見したい欲求にいきつく。
しかしさらに窓を見ていると「窓を見ている自分」に対する違和感が湧く。
その違和感が恍惚なのだと言う。
生島は、石田に一緒に窓を覗き見しようと勧誘するが、石田はそれを(表面上)断る。
生島は自宅にいる四十過ぎの寡婦と、何の愛情もない関係を続けていた。
そして不意にカフェでの会話を思い出し「窓を開けながら行為に及ぶ」ということを思いつき、その妄想にひとり興奮する。
石田は、カフェでは覗き見の勧誘を断っていたが実は興味があり、1人崖上にくるようになっていた。窓を見下ろす石田。確かに、ベッドシーンを覗き見したい気持ちも湧く。しかし、なかなかそんな窓には出会わない。
生島は、崖の上に佇む影をみて、自分が説得した石田が来ているのだと思い、さらに満足する。
あれは俺の空想が立たせた人影だ。俺と同じ欲望で崖の上に立つようになった俺の二重人格だ。俺がこうして俺の二重人格を俺の好んで立つ場所に眺めているという空想はなんという暗い魅惑だろう。俺の欲望はとうとう俺から分離した。あとはこの部屋に戦慄と恍惚があるばかりだ。
そしてある晩、石田がまた窓を覗きに崖上に来ていた。いくつもの日常の窓の中、ある産婦人科の窓に「死」の瞬間を見る。ベッドシーンを見ようとしていた彼が突如間接的な死の場面をみたことで、痛烈に「もののあわれ」を感じる。
「彼等は知らない。病院の窓の人びとは、崖下の窓を。崖下の窓の人びとは、病院の窓を。そして崖の上にこんな感情のあることを――」
歪んだ性癖を、他者の視点を挟むことで自らの手をくださずに「行為者」を増やしていく。ある種宗教のような話ですが、梶井基次郎の作風にはこのように自分の気持の「代行者」を仕立て上げるものが多く、この話は特にその色が濃くあらわれています。読者はその濃厚な闇に囚われることで、さらなる代弁者となるのでしょう…
闇(病み)レベル:[jinstar5.0 color=”#ffc32c” size=”16px”]
『愛撫』
「私」の妄想話。
常日頃、猫の耳を「切符切り」でパチンとやって見たくなる。きっと猫の耳はそんな危険に曝されても、痛がらないある種無敵なものなんだと信じてやまない。しかし、ある日私は猫の耳を噛んでしまう。すると鳴き声を上げる猫。無敵ではないと知り、失望する。
そして次は「猫の爪を全部切る」妄想をする。「爪=猫の存在意義」をすべて切れば、猫は死んでしまうのではないか?
木登りができない。
人に飛びかかることができない。
爪を研げない。
その度に自信をなくし、絶望し、恐怖し、遂には死んでしまうのではないか?
さらに、女性が「猫の手の化粧道具」を作って使っている夢を見る。
散々猫を妄想の道具に使った挙げ句、猫とじゃれ合う私。
仔猫よ!後生だから、しばらく踏み外さないでいろよ。お前は直ぐ爪を立てるのだから。
全くもって人間は勝手な生き物です。しかし、残酷な妄想でも、妄想にとどめておけば誰もがやっていることだし、それを咎める人はいないのです。
…まぁ、小説に書いてる時点で誰かに咎められそうなものですが(笑)
闇(病み)レベル:[jinstar5.0 color=”#ffc32c” size=”16px”]
『闇の絵巻』
私=梶井基次郎が、療養地で感じた「闇」への愛を綴る短篇。
深い闇の中で味わう安息。誰の眼からも隠れてしまう。巨大な闇と一如になった感動。
単純で力強い風景、闇。闇の中ですれ違った男に対してもこう綴る。
自分も暫くすればあの男のように闇のなかへ消えてゆくのだ。誰かがここに立って見ていればやはりあんな風に消えてゆくのであろう
濃い闇を長年経験した梶井基次郎にとって、都会のどこに行っても電燈の光がある夜を、薄っ汚く思わないではいられないのだそう。
「闇=死」に加え、「闇=安息」をダブルミーニングさせる梶井基次郎。この話には、不安や焦燥が見当たりません。どこか達観してきているのだとおもいます。
闇(病み)レベル:[jinstar5.0 color=”#ffc32c” size=”16px”]
『交尾』
前半は猫、後半は河鹿(カジカガエル)の求愛から交尾に至るまでを、こっそり隠れてみている「私」。
かなりの変態行為ですが、その文体は、まるで生物学者かのように清々しい。ここまで「生物の生」の生の姿に迫った小説は数少ない。それほど素晴らしい作品です。
芥川龍之介が描いた河童の世界に対し、河鹿の世界は案外近くにあるものだ。なんて冗談を言ってみたり。この話に登場する「私」は、無邪気で無垢で、子どものような魂ではしゃいでいるようです。
ぜひこの世界観、本当の文章に触れていただきたいと思います。
闇(病み)レベル:[jinstar4.0 color=”#ffc32c” size=”16px”]
『のんきな患者』
肺を病んでいる「吉田」が主役の客観小説。
身の回りの世話をしてくれる母親、そして療養所での暮らしの周りで囁かれる親戚の死、生に執着し様々な薬に縋る人びと、死の運命から逃れようとする人々を戦略的に勧誘しようとする宗教家の活動…
満ち溢れる「死の気配」を感じながらも、そこまでは切迫した雰囲気を感じさせない吉田の行動と思考。のんきな患者のタイトルどおりですが、梶井基次郎は本作を「のんきな患者がのんきな患者でいられなくなるところまでを書く」と宣言していたそうです。
そして、本作を仕上げた後、逝去します。
最後、貧富の差と生存率の差を述べるシーンがありますが、そんなことを思っている段階で切羽詰まってはいない感じがありますね。
個人的には、「肺を患ったある男のブログ」を読んでいるような、生活感があり感情も豊かに表現されている作品だと感じました。
闇(病み)レベル:[jinstar3.0 color=”#ffc32c” size=”16px”]
最後に
いかがだったでしょうか。
ざっとのあらすじをまとめましたが、実際に読まれる際に、もっと面白く感じてもらえるような情報になっていれば嬉しいです。
ぜひ、梶井基次郎の「闇」「死」に徹底的に向き合い紡ぎ出された20の短編集。それぞれの光と闇を感じながら、夭逝の天才作家が繰り出す秀逸な日本語の数々を味わっていただきたいと思います。
時代を越えて読みつがれる名作です。
『檸檬』梶井基次郎
文庫: 352ページ
出版社: 新潮社; 改版 (2003/10)
梶井基次郎『檸檬』の目次
檸檬
城のある町にて
泥濘
路上
橡の花ーー或る私信ーー
過古
雪後
ある心の風景
Kの昇天ーー或はKの溺死
冬の日
桜の樹の下には
器楽的幻覚
蒼穹
筧の話
冬の蠅
ある崖上の感情
愛撫
闇の絵巻
交尾
のんきな患者
梶井基次郎『檸檬』の読了時ツイート
32冊目
梶井基次郎『檸檬』この人は、死の入り口から生を見つめているのだろうか。
代表作「檸檬」を始めとする20の短編。どれも彼岸に咲く鮮やかな曼珠沙華の、花弁の裏側の色鮮やかで、しかし濃厚な陰影を宿している様です。
血が渇き黒ずんでゆく様な、甘美な秀作たち。単なる絶品です。#読了 pic.twitter.com/rFKSsALKIW
— 右脳迷子@ざっくり庵 (@unoumaigo) April 8, 2019